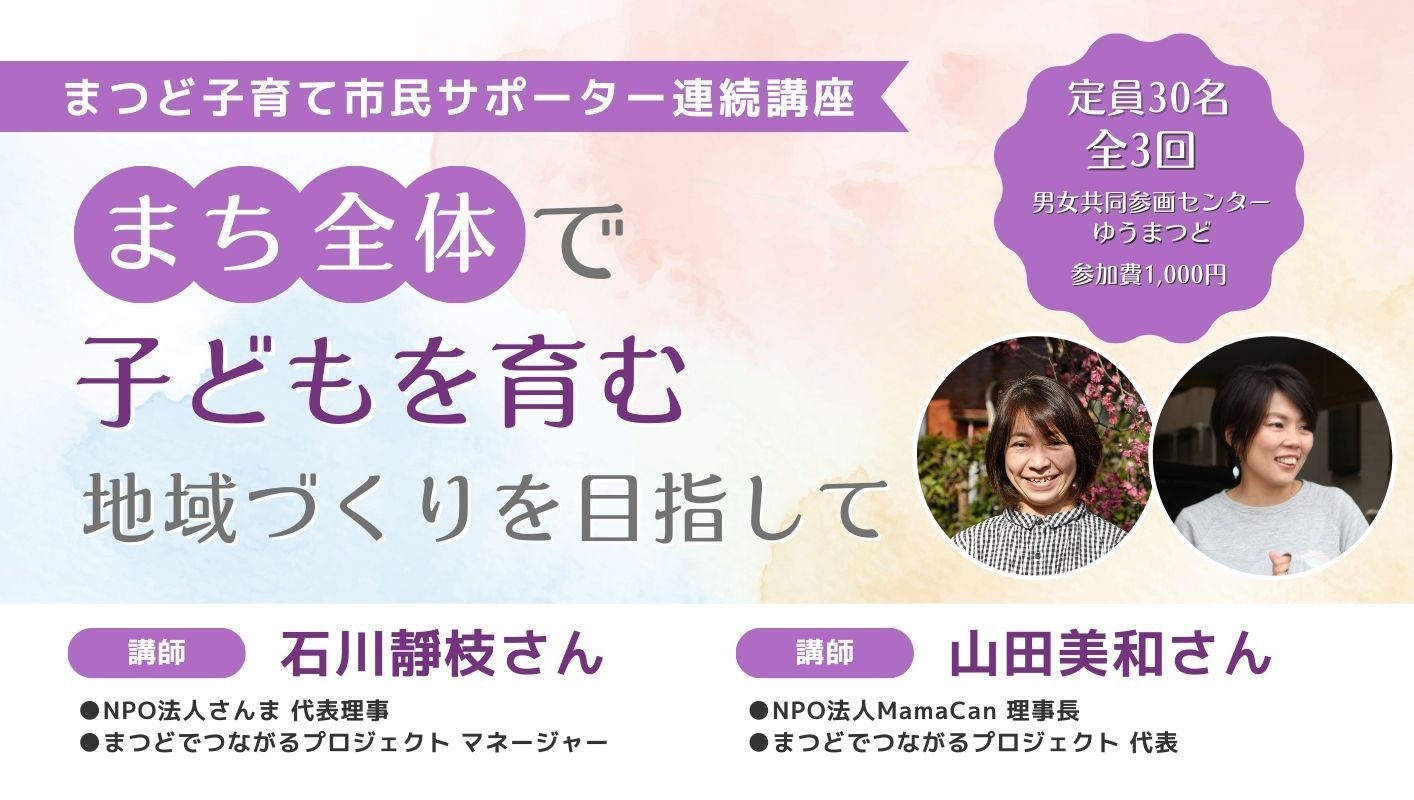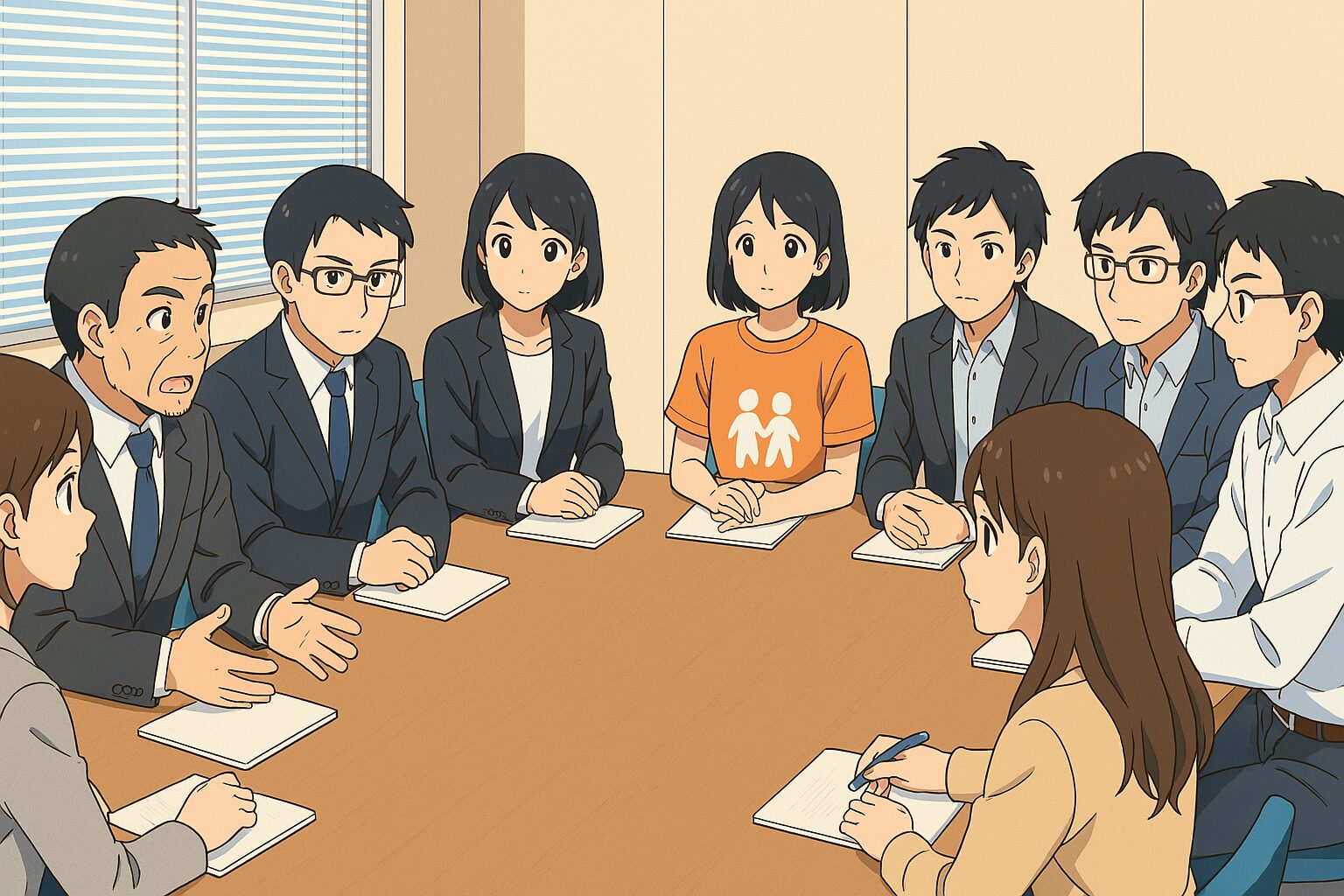2024年12月25日、松戸市市民会館にて、松戸市子ども・若者の支援を考える会とまつどでつながるプロジェクト運営協議会の共催で開催されました。行政や教育・福祉関係者、地域活動・市民活動関係者が46名集まり、青年期に起こりがちな孤立や、年齢やライフステージの変化に伴って途切れがちな支援について情報や意見が交わされました。
<開催概要>
■テーマ:青年期における現状の共有と連携の糸口を探る
■日時:令和6年12月25日(水)14時~16時半/終了後名刺交換タイム
■開催方法:市民会館301号室
■参加者:46名(行政職員、医療・福祉関係者、地域・市民活動に関わっている方など)
■主催:松戸市子ども・若者の支援を考える会・まつどでつながるプロジェクト運営協議会・松戸市子ども政策課
<開催の様子>
支援のバトンをつなげるための場〜共催団体紹介
最初に、つながるプロジェクト運営協議会から「連携の糸口を見つけるために、まずは支援者同士が互いに知り合うこと」という円卓会議の趣旨や目的を説明しつつ、まつど子ども若者ネットワーク(まこネット)の紹介がありました。また円卓会議を共催している子ども政策課からは、次年度から新しくなる子ども総合計画について紹介していただきました。
・まつどでつながるプロジェクト運営協議会(阿部)
つながるプロジェクトは設立から一貫して「つながりにくい人とどうやってつながるか」をテーマに活動を展開する団体です。どうしても生まれる組織や活動のすき間に思いを馳せ、組織や個人が歩み寄ってできることを考えるための円卓会議だということでした。
・まつど子ども若者ネットワーク(まこネット・桑田)
2018年から活動を開始して、オフラインやオンラインでの支援者の集まりを開いています。支援者が安心して弱音を出せる環境が、協力関係を築きやすい環境であり、当事者である子ども・若者の孤立を防ぐことにつながると話しました。
・松戸市子ども政策課(鈴木課長)
来年度から子ども総合計画の第3期が始まるとのことで、計画の概要の説明がありました。子どもの権利を踏まえて「すべての子どもに“十人十色”に輝く未来を!」を基本理念に据え、支援が特定の年齢に途切れぬように策定されている点も説明されました。
<グループで対話された内容(一部)>
●子どもや若者の話をきちんと聴けているのか?
続けてグループごとに「大人が感じる、子どもや若者の間にある不安」について話し合いました。あるグループでは、次のような課題共有がありました。
・「教育や就職の格差やコミュニケーション、社会の平安などに不安要素しか感じられず辛い」
・「闇バイトに代表されるような危険なSNSの使い方が蔓延している」
・「相談を受ける中で親とのやりとりが先行することが多く、親と子から平等に話を聞けているのか不安」
・「親や大人から見える子どもの姿と、子ども自身が抱える想いのすれ違いがある。子ども自身の不安を増大させる対応をしていないか心配」
・「親御さんの支援から入ることが多く、子どもとは価値観の違いなど世代の違いを感じることも多い」
●子どもや若者の中に地域で大切にされている感覚を育てたい
休憩を挟んで、「変化を起こせそうなこと」「協力できそうなこと」について、グループで話し合いました。
・「孤立を防ぐつながりを増やしたい。やはりリアルのつながりから大切にしていきたい」
・「相談先、安心できる先を増やすのが一番。とはいえ、子どもの居場所はハードルがあり、行くまでに時間がかかる」
・「やはり挨拶が基本なのでは。大人がバウンダリーの意識を持ちたい」
・「雑談できる関係性から始めたい。その意味では今つながることができているボランティアの子どもたちとの縁を大切にしたい」
また、子どもの声を聴く仕組みが構築されているフランスの事例も紹介されました。親の匙加減一つで子どもの人生が決まってしまうのではなく、社会全体で子どもを育てる仕組み、家族丸ごとケアする仕組みが共有され、討議が盛り上がりました。
●地域でケアがつながり、ケアし合えると良い
最後に各グループからの討議内容の共有がありました。
・「子どもの話と親の話が噛み合わないことが多く、どちらの話もそれぞれに聴ける人がいると良い」
・「親も子も情報過多の中で本当に必要な情報が得られていない」
「子どもが意見を言えない背景には、意見を言っても聞いてもらえなかった体験がある」
といった内容が語られました。
今回の円卓会議では、先に不安というネガティブな内容を語り合い、そこから変化の種になるポジティブな語り合いへと移行しました。まこネットの桑田さんより「情報も溢れているけれど、そこには感情もきちんとあるはず、ケアがつながり、ケアをし合える地域を育てたい」と述べて、会議を締めくくりました。
【主催】まつどでつながるプロジェクト運営協議会・子ども政策課